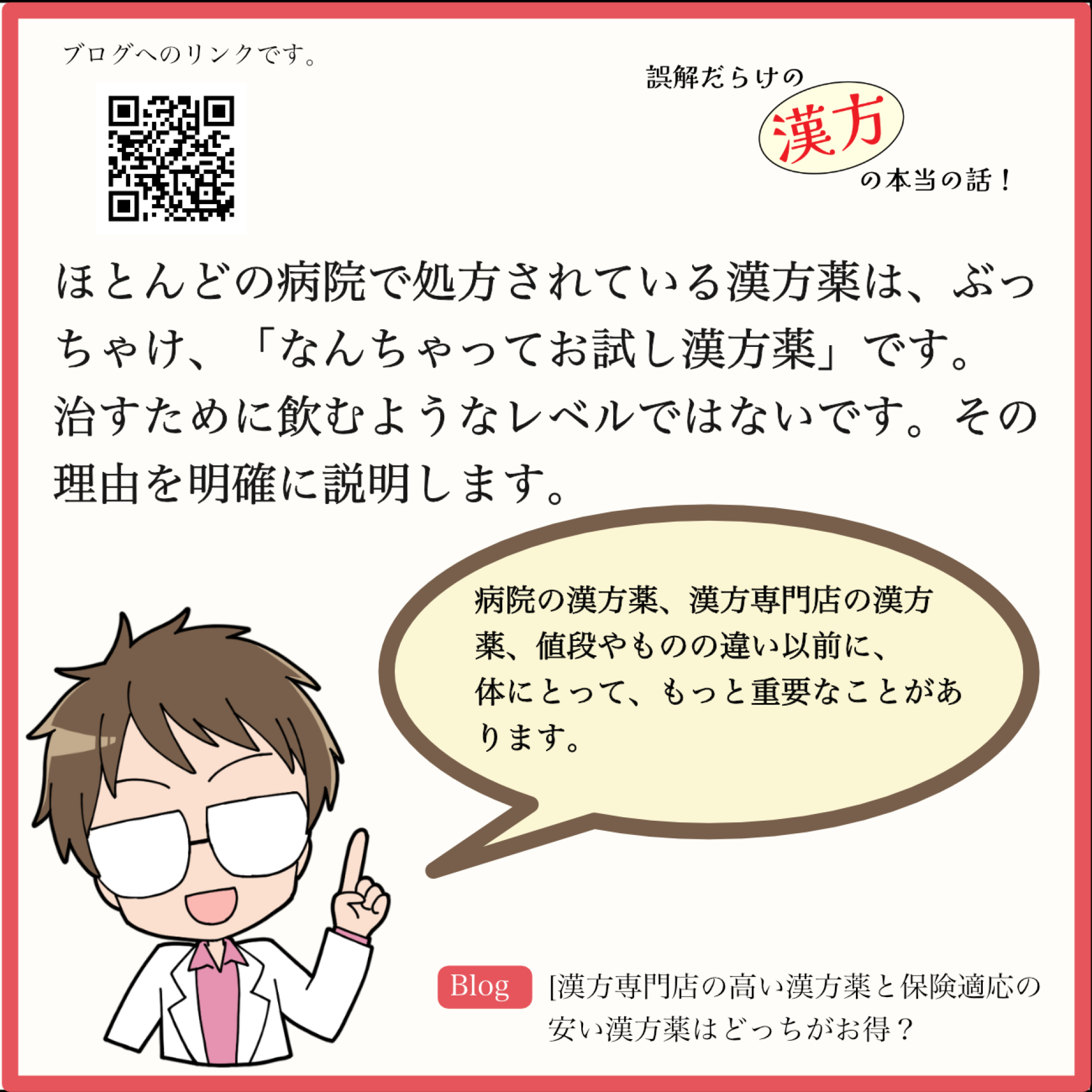
病院の漢方薬って大丈夫なの?保険適応の漢方薬は実は信頼できないその理由
- 医者の漢方薬の処方は本当に安心できるのか?
- 病院の漢方薬は本当に成分がしっかりしているのか?
- 実は病名や症状から漢方薬を選んでも効かない
- 本当に良い漢方治療は安易に「病院だったら安心」と決められない理由
うちに通っておられる患者さんから、「先生のその話、聞き飽きたよ!」って言われそうですが、漢方って本当に間違った知識しか伝わってないんだなと思うので、漢方が一般の人だけでなく、医者にすら誤解されている話をしたいと思います。
うちに通っておられる患者さんが、友達から「なんで、わざわざ値段の高い漢方専門のお店に通ってるの?病院だったら、保険がきくから安いじゃん」って言われたそうです。
確かに『治るか? 治らないか?』の治療ではなく、『安いか? 高いか?』の値段だけで考えれば、断然、保険適応の漢方薬の方がお得ですよね。
ネット検索で見つけた某質問サイトでは、「漢方の店でなく、からだのことだから、病院のように安心できるところで処方してもらったほうがいいですよ」と答えているのも見つけたりしました。
ただ、その答えを支える理論も情報ソースとなるウェブサイトもなかったりするのですが、ああいう「”パンダさん”という匿名で素性がよくわからず、なおかつ情報ソースのウェブサイトのURLもない答え」なんかを真に受ける人がいるのだろうか?と、僕からすると不思議です。
それも「体のことなのに、匿名の奴に質問なんかする?」って感じですね。
今回は、漢方自体が誤解されすぎているので、3つの誤解をリスト化して説明していきたいと思います。
この誤解を知れば、医者から漢方薬を出してもらうのは、大丈夫じゃないかもしれないと思うかもしれません。
漢方で一般的に誤解されているリストは以下の通りです。
1 医者の漢方薬の処方は本当に安心できるのか?
2 病院の漢方薬は本当に成分がしっかりしているのか?
3 実は病名や症状から漢方薬を選んでも効かない
これらを1つずつ詳しく解説していきます。
本当のことを知った上で、自分に最適な方法を選ぶのが良いかと思います
医者の漢方薬の処方は本当に安心できるのか?
「病院の漢方の方が安心」という話がありますが、そもそも、医者の方が安心という根拠は、『医療について専門的に勉強してきた』という知識と実績ですよね。
確かに医者は西洋医学については、何年も勉強していますが、漢方に関しては、医大で学びません。
勉強したとしても、ごくごく一部の漢方薬名や漢方薬の成分を勉強するだけです。
残念なことに漢方薬は、西洋医学の薬とは全く違うものなので、何かの成分で効かせるわけじゃないのですね。
また、漢方薬は病名や症状ではなく、体質に合わせて選ばないと効果がないのですが、「漢方薬を使って治すための体質の診断の方法」や「体質に合わせて漢方薬を選ぶ方法」など、漢方の医学理論は全く学びません。
せいぜいが某漢方薬メーカーの勉強会に月1、2回、顔を出すくらいです。(勉強というよりもイベント事)
この勉強会、実は僕も医者に紛れて参加したことがありますが、はっきりいって内容が幼稚すぎてひどかったです。
何回か参加しましたが、どれもド素人向けの漢方薬のさわりか、「◯◯病に◯◯の漢方薬を使ったら治った」みたいな、「そんな簡単な選び方で治るわけねー」というマニュアルの方法を発表しているだけでした。
つまり、残念ながら医者だからって、「漢方について、じっくり勉強してきた」という『知識』はないのですよ。
そして、実績の方ですが、漢方薬は、本来、体質を分析して、選びますが、医者は、体質を分析せず、マニュアルをみて、病名や症状から漢方薬を選びますが、これはいわば、頭痛の人に下痢止めを出しているようなものなので、何百人とみようが、実績にも経験にもならないのですね。
西洋医として開業してから、漢方の勉強会に参加した程度なら、今の時代だったら、一般素人の人で漢方に興味がある人の方が、よほど詳しいかもしれません。
日本で一番有名な某漢方薬メーカーの勉強会だからって、別に専門的でもなんでもなかったのですね。
「嘘でしょ?」と思われるかもしれないですが、東洋医学に関しては、医者は、本当にど素人なんです。
病院の漢方薬は本当に成分がしっかりしているのか?
漢方薬は病院の薬と違って、化学的に大量生産できません。
漢方薬の中身である生薬は、松茸などの希少価値の高い野菜みたいなものです。
松茸もそうであるように、品質はピンからキリまであります。
病院の薬なら、有効成分は、化学合成物なので一定ですが、漢方薬はそういうわけにいかないし、そもそも漢方薬には有効成分など存在しません。
存在しないというか、どの成分がどう効いているのか全く特定できないのです。
(これにはそもそも病院の薬と治療目的が違うというのもあります)
漢方薬の有効成分を研究しているところもありますが、漢方薬は病院の薬とは全く違うものなので、有効成分の話なんて現在のところは、何の治療の足しにもなりません。
「治療と関係ないけど趣味でやってれば」というレベル。
漢方薬を構成している生薬は、食べ物みたいなものなので、むしろ、良い食材を見抜く目利き的な能力が必要です。
昔、週刊新潮で、「ツムラの漢方薬は宣伝と違って、農薬がひどすぎてツムラの社員は自分の会社の漢方薬を飲まない」という記事がありました。
漢方薬の場合は、化学成分で作っているわけではないので、病院の漢方薬の方が良いかどうかは全く関係ないのです。
むしろ保険適用の薬は薬価といっていわゆる定価を会社ではなく、国が決めます。
そしてこの薬価を決めることに関わる健康保険の財源である税金は慢性的な大赤字なので、年々、薬価を下げていきます。
ところが、漢方薬は貴重な野菜みたいな相場もの。
つまり、各生薬は、値段がピンからキリの上に、定価は勝手に安く設定される…となると、利益を出そうと思ったら、仕入れコストを下げるしかないのです。
つまり、保険適用の漢方薬は、「最底辺の安い生薬を探さないといけない」ということに、ならざるえないことが想像されます。
また、投資をされている方ならおわかりになるかと思いますが、保険適用の漢方薬を販売している会社は、ツムラです。
ツムラは一部上場会社で、上場会社の第一の使命は、『とにかく利益をあげること』
治ることは、売り上げにつながるかもしれないですが、上場会社は、株主のもので、株主達が、欲しているのは利益なので、治ることよりも儲かることのほうが重要なのです。
実は病名や症状から漢方薬を選んでも効かない
漢方薬は東洋医学のルールで使って、初めて効果を発揮します。
漢方薬は、西洋薬の医薬品のルールを無理やり当てはめて、医薬品としています。
医薬品の法律上、漢方薬は西洋医学の医薬品のルールに則って、説明されていますが、そもそも西洋医学と東洋医学は何の関係もありません。
漢方は約2000年前に中国で発展してきた医学で、今の病院の医学は約200年前あたりからヨーロッパやアメリカで発展してきました。
一般的には医薬品の法律上、西洋医学のルールにあてはめて、病名や症状から漢方薬を選んでいますが、あくまで医薬品販売としての法律上の運用であって、治療を考えての選び方ではありません。
当然ですが、法律がどうであれ、漢方薬は東洋医学(漢方)のルールに則って使わないと効果を発揮しません。
『東洋医学の検査方法』
『東洋医学の体質の判断方法』
『東洋医学の効果の考え方』
これらの『漢方薬を使って治すためのルール』は2000年前からありますから、血液検査とか、西洋医学の病名なんて何の縁もゆかりもないのです。
したがって、病院がやっているような西洋医学の病名や症状からマニュアルをみて漢方薬を選ぶというものは、法律上は正しいですが、治療上は漢方の世界には存在しないデタラメな方法になります。
本当に良い漢方治療は安易に「病院だったら安心」と決められない理由
医者は、漢方の勉強をしていません。
漢方薬は化学的な有効成分で効かせるわけではありません。
漢方薬は、漢方独特のルールで検査したり、体質を判断したり、漢方薬の効果を考えます。
西洋医学の知識は、漢方薬で治療する際に断然、ないよりはあったほうが良いですが、残念ながら、西洋医学の知識があるからといって、漢方のプロフェッショナルになれるわけではないのですね。
つまり、漢方治療に関しては、医者も、これから素人向けの漢方セミナーに行こうとしているあなたも、『大して差がない』のです。
下手したら漢方に興味を持っている友達の方が医者より詳しいと断言できます。
もちろん、病院でも本格的な漢方治療をしているところはあります。
しかし、結局、そういう病院は、実費で月3万円くらいだったりして、保険適応ではないのですね。
当たり前ですが、西洋医学は、医大でしっかり勉強したことが安心、信頼の保証になりますが、こと漢方に関しては、西洋医学をバリバリ勉強してきたことは、漢方においては、何の保証にもならないのです。
「漢方薬が高いか? 安いか?」よりも、その人自身が、医者なのかどうかではなく、漢方家として、優れているかどうかを見極めないと、延々と治りもしない漢方薬を飲まされ続けることもありますよ。
また、漢方薬の副作用は、『体質と漢方薬が合っていなければ』起こります。
ほとんどの医者や漢方薬局の先生は、病名や症状に当てはめて漢方薬を選び、体質の分析ができません。
「体質を分析して選んでいない」ということは、医者は普通に選んでいるつもりで、本来の東洋医学からすると、最初から間違った漢方薬を選んでいるのです。
間違った漢方薬を飲むことによって、よりひどい病的な体質になることもありますので、漢方の治療理論で漢方薬を選べない人、つまり体質分析から漢方薬を選ばない漢方薬は、むしろ飲まない方がマシだと思います。
つまり、病院の漢方薬は、モノとしては漢方薬かもしれませんが、効果を発揮するように選ばれていないので、治療が、部の悪い運任せになっているのですね。
当店では、人それぞれの体質を分析して、その人独自の原因に合わせて漢方薬をお選びします。
ご希望の方は、概要欄にネット相談や店頭相談の予約カレンダーを貼ってありますので、ご相談ください。
あなたの現在の体質や原因を判断して、治療方針をご提案いたします。
相談は無料です。
●更年期障害や不眠などで、お悩みの方は、こちらの「漢方無料相談」から送信してください。
●お問い合わせは、こちらから送信してください。
●店頭相談のご予約は、こちらから、ご予約ください。(店頭も初回の相談は無料です)
日本全国オンライン相談受付中!
※全国(北海道、青森、岩手、仙台、東京都内、群馬、横浜、富山、福井、滋賀、名古屋、京都、奈良、大阪、兵庫、岡山、福岡、大分、鹿児島など)からネット、メール、電話、LINEやメッセンジャーなどのテレビ電話などのオンライン相談を受付中です!
【引用先及び参考図書・Webサイト】
◯ 漢方概論:創元社
◯ 漢方方意ノート:創元社
◯ 漢方臨床ノート(論考編):創元社
◯ 金匱要略ハンドブック:医道の日本社
◯ 傷寒論ハンドブック:医道の日本社
◯ 素問:たにぐち書店
◯ 漢方治療の方証吟味:創元社
◯ 中医診断学ノート:東洋学術出版社
◯ 図説東洋医学:学研
◯ 中国医学の秘密:講談社
◯ 陰陽五行説:薬業時報社
◯ まんが漢方入門:医道の日本社

関連した記事
- 病院の漢方薬を飲んでも大丈夫?「ツムラが国民を欺いた!!漢方の「大嘘」について」
- ツムラが国民を欺いた!!漢方の「大嘘」週刊新潮の記事です。ゴシップでも大げさでもない真実。人知れず保険適用の病名マニュアルで処方された漢方薬の強い副作用で病気が余計にこじれている人がいます。
- 自分の症状から選んだ漢方薬が効かない理由
- 病院で処方してもらった漢方薬がなぜ、効かないのか?その理由を解説します。
- 問診も取らずにどうやって漢方薬を選ぶのでしょうか?(病院の漢方薬)
- 以前に病院で漢方薬を処方してもらっていた患者さんからの素朴な疑問です。なぜ、問診もとらずに数百種類もある漢方薬の中から1つを選ぶことができるのか?答えを考えてみました。